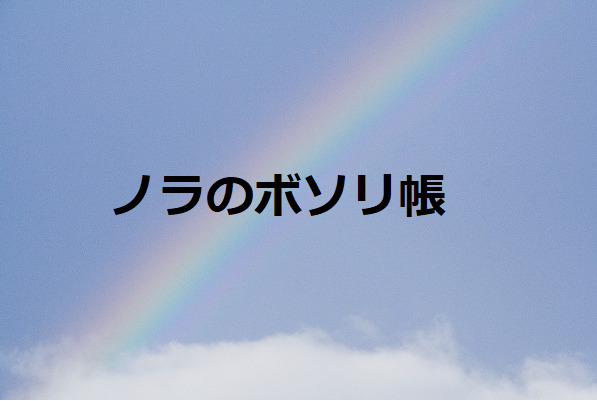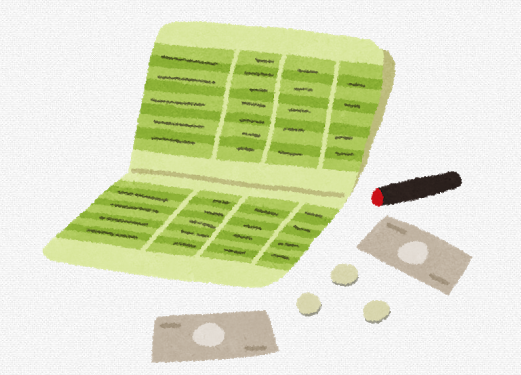こんばんはトヨクニです。今回は田原城(たはらじょう)についてしみじみと語ってみようと思う。訪問したのが2017年頃だったと思う、所在地は愛知県田原市田原町にあり現在は田原城址と呼ばれている。石垣、水堀などの遺構の他に昭和の頃に建てられた城門や櫓などの再建造物もある。田原市の比較的中心部にあるので少し歩くことにはなるが、公共交通機関で行くのも可能だと思う、もちろん俺は車で訪問したけどさ。まぁ広い専用駐車場もあるので車で行くのが無難だと思うけどね。

田原城は文明十二年(1480年)戸田宗光という者が築かせたと言われている。戸田氏はこの田原城を本拠地にして三河地方や一時期は知多半島にまで勢力を拡大していたが、後に松平氏や駿河の今川氏に従属することになった。天文十六年(1547年)に駿河の今川氏へ人質として送られる松平竹千代(徳川家康)を護衛する任務を請け負ったがこの時の当主であった戸田康光は今川氏を裏切り人質であった竹千代を尾張の織田信秀の元に送り届けてしまう事件が発生する。要は信秀に売り渡した訳ね

この一件で今川義元は当然ながら激怒し、田原城に兵を送り込みこれを攻略、康光とその一族は城に籠って戦うも討ち死にしてしまい戸田氏による支配は終焉を迎えることになる。その後は今川義元の家臣が城代を勤めていたが、桶狭間の戦いで今川氏が没落し代わりに徳川家康が台頭してくるとこの田原城も永禄八年(1565年)に家康の手に落ち、以降は家臣の本多広孝という者が城代を勤めたそうだ。天正一八年(1590年)に家康が関東に転封されると代わりに池田輝政がこの地を支配するようになり、その家臣である伊木忠次という者が城主になる。現在残っている石垣や曲輪はこの時代に整備されたモノなんだそうな。江戸時代に入ってからも藩庁として田原城は存続していたが、明治時代を迎えるとその役目も終わり、明治五年(1872年)に建物類は解体され廃城となった。概要はこんな感じかね


大きな水堀を構えいくつかの曲輪に囲まれた田原城だが、このような形状になったのは池田輝政が支配していた頃で築城された当時はこの地域はまだ干拓されておらず海水に囲まれた天然の城塞だったようだ。この近くに吉田城という大きな城跡があるのだが、この地域に限定すれば田原城はそれに次ぐ規模だと思うけどね。水堀を眺めた後に再建造物の大手門をくぐり抜けると左手に二の丸跡、右手には三の丸跡がある。二の丸跡には博物館が建てられていたが訪問した時間が早かった為かまだ開園していなかった。

まぁ興味ないから別にいいけど・・・三の丸跡は護国神社が建立されていた。適当にフラフラ見回って本丸跡へ向かったのだが、何やら催し物の準備をしており、その後も続々と人が入ってきたので早々に退散することにしたよ。本丸跡から駐車場へ向かう通路があり帰りはそこを使ったのだが途中に井戸跡らしき遺構があったね。当時のモノかどうかは分からんがね。こんな感じで探索は終了

攻略難易度★
俺の名はノラネコ、まぁそんなのはどうでもいい。俗に言う「氷河期世代」の初期型で同年代の連中(特に♀)からは蔑まれている。俺はなにもしてないのに・・・そんな訳で性格はかな-り荒んでいる